- トップ
- 部紹介
- 歴史・戦績
- 過去の特集
- 第61回(2007年度)ライスボウル特集
- 第61回(2007年度)ライスボウル特設コラム(6)
第61回(2007年度)ライスボウル特設コラム(6)

爆発(explosion) -史上最高のパスゲーム-
QB/WRコーチ 小野 宏
| (1)“日本代表”との対決 | (5)OLたちの詩 | (9)ロジスティックス |
| (2)二つのノーハドル | (6)ショットガンの5年 | (10)カズタの物語 |
| (3)人が変わる時 | (7)ラン&シュートへの挑戦 | (11)後世畏るべし |
| (4)ゴール前の罠 | (8)マネジメント改革 |
| (6)ショットガンの5年 後手に回った戦術改革 関学として部史上最高のパッシングゲームが構築されていたことを証明できたことが我々にとっての喜びであったことはすでに記したが、このオフェンスがどのようにしてできたのかを書いてほしいというのが石割アシスタントディレクターの元々の依頼だった。だから、そのことについてもう少し書き連ねていきたい。 まず、5年前の2002年11月。我々はリーグ最終戦で、ショットガンを導入して3年目の立命館大に14-48で完敗した。その夜、コーチの慰労会でショットガンの導入が俎上に上った。米国で当時、ショットガンのオフェンスが急速に増えだしていた。その大きな潮流の源泉の一つだったノースウェスタン大学の情報はフットボール留学していた大村和輝氏(現オービック・シーガルズ攻撃コーディネーター)から聞いていた。その一部も立命戦に組み込んだのだが、全面的にショットガンを導入することには不安があった。せっかく築き上げた我々のIフォーメーションとワンバック隊形のダイレクトスナップ(DS)からのオフェンスは十分に機能していた。それをガラリと模様替えするとなれば、蓄積してきた多くのものを捨て、枠組みから作り直さなければならない。口では簡単に言えるが、戦術の大きな変更は手探りで進めていかなければならない。当然、戦術的な質の低下を伴う。 しかし、チームにとってより重要なことは、攻撃がそれをすることで守備が年間を通じてこのショットガンに慣れ親しむことができる。そうでないと、守備は立命と試合をするための2週間だけしかショットガンオフェンスと実戦を積むことができない。そもそもショットガンの優位点と問題点は、実際に自分のチームで取り組んでみなければ明確には分からない。ライバル立命館の後を追う形になるのは内心忸怩たる思いがあったが、背に腹は変えられなかった。 「併用」の誤算 当初はショットガンとDSの隊形との併用を頭に描いていた。例えば、我々のオフェンスが中核に据えていたIからのゾーンプレー(ラン)は、ショットガンでも同様に使用することが可能だと考えていた。 ところが、実際にやってみると併用は思うようにいかなかった。同じゾーンプレーでもIのTBからとショットガンのRBの位置からでは、走るコースを同じにしても微妙にタイミングが異なる。 我々はプレーの緻密さを身上としている。タイミングや角度の微妙な違いで結果的に二つのプレーと認識せざるを得なくなり、一つのプレーをショットガンとDSの双方で持てば2倍近い練習量を必要とする羽目になった。そうなると二つを併用することでプレーの種類が半分に減り、次第にあからさまな傾向が出るようになった。 そのため、ショットガンに専念する方針に転換していったのだが、そこにも問題があった。オフェンスにとって必須の構成要素となるプレーが、ショットガンからはうまくいかないものが少なくなかったのだ。そうした欠落した要素を一つ一つ揃えるべく、効果的なプレーを新たに開発しようとしたが、試行錯誤が続き、遅々として進まなかった。オフェンスは暗中模索といった状態に陥り、戦術面で方針が揺れ動いた。 空の引き出し そんななか、2003年夏合宿でチームの主柱だった4年生のLB平郡雷太君が亡くなった。大きな喪失感とチームの中心部に空いた空洞は埋めようもなかった。 鳥内監督が喪に服している期間に行われたリーグ第2戦。関西大学との対戦は、試合の序盤からプレーを読まれていることにすぐに気がついた。フォーメーションからなのか、バックの位置からなのか、最初のアクションをキーにしているのか。2部から上がってきたばかりの関大だが、春の関関戦でのデータを元に関学オフェンスを十分に分析して対策を立てており、プレーが非常に通りにくい状態に陥ってしまった。しかし、戦術の引き出しが少なく、「それを止めにくるのなら、これをして困らせよう」というプレーの整備が追いついていない。対応は後手に回り、TDを奪えずに55年ぶりの敗戦を喫した。 翌年のリーグ第5戦。全勝対決の立命にはさまざまな新しいプレーを組み込んで30点を奪って勝ったものの、翌節にすでに3敗していた京大に敗れた。これも簡単に言えば、京大守備に関学攻撃の本質的な問題点を的確に付かれたことが大きな敗因である。関学らしい洗練されたゲームをするには、さまざまな状況に対応できるプレーが過不足なく整っていることが条件だが、それがまだ整備されていなかった。こうした戦術的な盲点は対戦相手に突かれて初めて自覚させられることも多い。結局プレーオフで立命にタイブレークの末に敗れた。2年先行している立命のショットガンの良いところばかりが目に付き、屈辱感に苛まれた。個々の体力、スピードで劣っているうえに戦術的にもアドバンテージを持っているとは言い難い。そのような状況では結局勝ちきれないことを思い知らされた。 |
|
コア・コンピタンスは? 空の引き出しを一つ一つ埋めていき、2002年以前と同様の戦術が揃うまでに結局4年近くかかってしまった。2006年に入ってようやくショットガンからでもさまざまな守備戦術に対応できるツールがそろったと実感できるようになった。 しかし、「核」になるものが確立されていなかった。2004年の立命戦に勝ったゲームはアンバランス隊形からのジェットモーションでのスイープを軸にしたもので、プレーオフも含めるとそこからプレーアクションパスやカウンターオプション、フェイクのQBオフタックル、シザースなどいろいろなバリエーションをそろえたが、これももともとのスウィープは前年に立命がWR冷水で我々からタッチダウンを奪ったプレーを取り込んで改良し、シーケンスを構築したものだ。 これらのプレー群はかなりの効果があったが、「核」にはならなかった。これらのアイディアは普遍的すぎた。誰でもできて成果が出やすいプレーだったからだ。苦心して創り上げたのに、翌週には近畿大学がすぐに真似をして、うまく立命館からゲインを奪っていたし、その後も法政大学が同じシリーズを使うようになり、2006年の甲子園ボウルでは第1プレーからこのカウンターオプションで丸田に独走タッチダウンを奪われた。 戦術面で中期的に優位に立つためには、他者が真似できないノウハウが組み込まれた戦術体系でなければならない。企業競争と同じで、No.1かonly oneでなければ生き残れない。他者が真似できる技術は、一歩先んじたとしても薄利多売の安売り競争に巻き込まれてしまうのと構図は同じである。我々にとってのコア・コンピタンス(核となる競争力)とは?これが2004年ごろからの我々の最大のテーマだった。 |
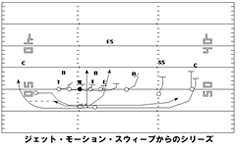 |
次へ |
|


